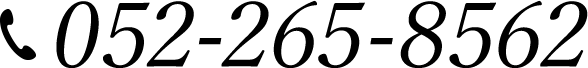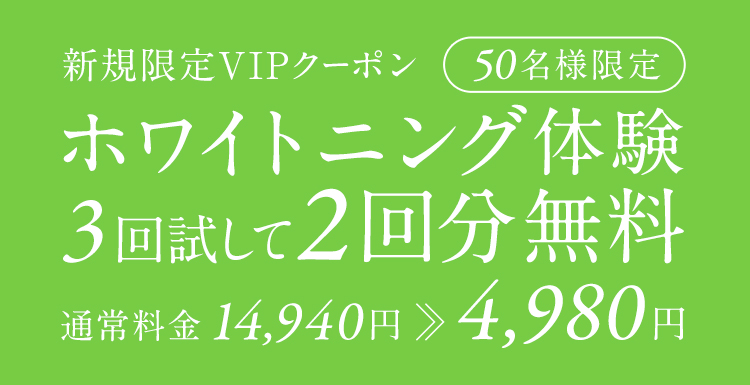【歯肉の構造と唾液腺のしくみとは】
こんにちは☆
歯と筋肉の構造について皆さんはご存知ですか?
歯は口の中で食べ物を噛み砕き、すり潰すためにあります。
乳歯は20本、永久歯は32本からになります。
食べ物を切るシャベル状の切歯、尖端が突出し、切り裂くための犬歯、すり潰しに便利な臼状の歯があります。
ヒトの歯は一生に生え変わることから二生歯と呼ばれていますが、
切歯、犬歯、小臼状は二生歯ですが、大臼状は一生歯で、新しく生え変わることはありません。
犬臼状は一生の間に最も長く使われているため、食生活の影響を反映して歯の溝がすり減り平坦化することがあります。
加齢により徐々に咬耗しますが、歯が破損することはありません。
溝がすり減ることで菌が溜まりにくくなると考えられています。
かみ合わせの異常や歯ぎしりなどの病気が関係していることが多いと考えられています。
🟠歯肉の構造
歯周病組織は歯頸部を取り組み咀嚼力に対応して、歯の破折や口腔内の異物、さらに食べかすが歯槽に進入を防ぐ働きがあります。
このうち歯肉は歯頸部周囲と歯槽骨を被う上皮性の粘膜で骨側は厚く角化しているのです。
歯と上皮の間にできる溝を歯肉溝と呼び、細菌が繁殖することで歯周病の原因となることが多いのです。
この歯頸部を取り囲む上皮と歯冠形態の変化が食べかすの溜まりを招き、そこに菌が繁殖し、歯と歯肉の間に蓄積してしまいます。
咀嚼運動には肉や歯周病組織に機械的な刺激を与え、食べかすを除去する効果もあります。

🟢唾液腺の構造としくみ
唾液腺は道管を持つ腺で大唾液腺と小唾液腺とに大別されます。
特に大唾液腺のうち、耳下腺は口腔前方の空間で上部の頬粘膜、顎下腺と舌下腺は舌の下に道管の開口部があり、ここから大量の唾液が出ます。
唾液は唾液腺で1日1〜1.5リットルもつくられ、その中にはアミラーゼという消化酵素が含まれ、食べ物の消化を助けます。
洗浄作用が大きく、常にお口の中を洗い流す働きや、口腔内を中和したり、リゾチームやペルオキシターゼ、さらにムチン、ラクトフェリン、免疫グロブリンなど多くの物質が含まれており、これらが虫歯を防ぎます。
また、唾液腺の有無は口臭も関係するのです。
消化では口から食べる時に食べ物をすり潰し、唾液と混ぜます。
食べ物は口唇で捕え、口腔の前方で大唾液腺である耳下腺からサラサラした唾液で食べ物に十分な水分を与え、後方に送り込み、顎下腺と舌下腺からややネバネバした唾液と混ぜ合わせ、食べ物が小さな魂となり咽頭、食堂、胃へと移動していきます。
小唾液腺は粘液性が高く、口腔内の保湿、乾燥防止に働きます。
唾液の分泌はみたり、嗅いだりする刺激と、
口の中に入った食べ物に含まれる化学物質による味覚、さらには、かみごたえ刺激などで唾液が分泌されます。
脳では交感神経と副交感神経によって反射的に調節され唾液が出ていきます。
大唾液腺の多くは舌顎と顔面筋を動かした時に物理的にも道管から唾液が押し出されます。
唾液は、加齢や咀嚼の機能低下、薬の副作用、導管に結石ができる唾石症などで分泌が低下します。
🔵歯の組織
歯周組織は歯の周囲にある組織で歯肉、歯根膜とセメント質、歯槽骨4つからになります。
骨と歯のセメント質の間に歯根膜という組織が存在し、
これらがシャーピー線維と呼ばれる強靭な線維によって結ばれます。
このシャービー繊維は、象牙質と隣接するセメント質と付着歯肉を結ぶもの、歯と遊離歯肉を結ぶもの、骨とセメント質を結ぶものの3種類の走行の異なる線維が歯と骨とを強く結合しています。
このように歯は堅固で弾力性を持つ結合により、
噛んだ時に歯に加えられる力を分散させ、スムーズな咀嚼を行います。
当店はホワイトニングの専門店です!
歯の黄ばみ汚れや着色については当店へお気軽にご予約くださいませ☆
皆様からのご予約お待ちしております♪
☆ご予約は下記からどうぞ☆
TEL 052-265-8562
LINE @klb5910y